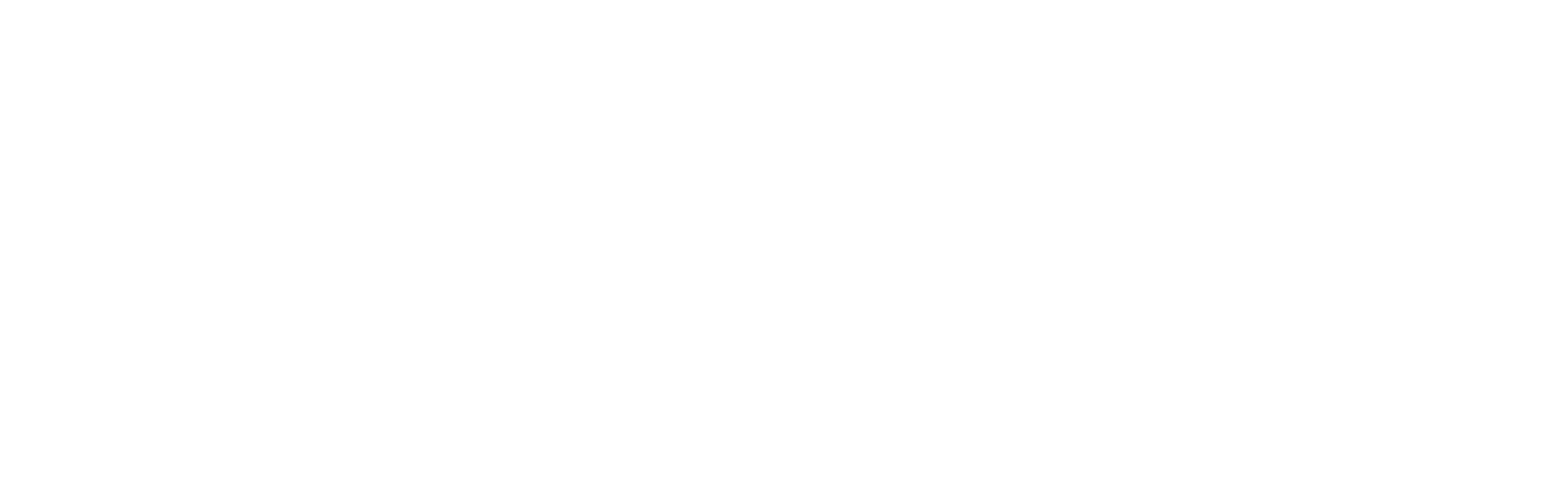何でもやるから、何でも学べる
現在は、主にアシスタントプロデューサーとしてドラマ制作に関わっています。アシスタントプロデューサーの役割は幅広く、キャストの身の回りのケアやスポンサーサイドへの配慮といった現場業務や、編集に関わるスケジュールや段取り作成、さらには脚本会議への参加やリサーチおよびキャスティングをはじめ、撮影時には「飲食物やスマートフォンなど小物のブランドが特定されないようにする」などといった細かい作業もおこないます。
まさに、その現場ごとに求められるポジションを何でもやる存在なのですが、その分、ドラマ制作の醍醐味をまるごと味わえる仕事だとも言えます。役者はもちろん、監督や脚本家、プロデューサーをはじめ、関わる人は大勢。それぞれの視点を学ぶことができ、「自分ならどうするか」と考えるきっかけにもなります。また、何より嬉しいのがドラマを観てくださった方々からの反応。知人や友人から届く「面白かったよ」の声はもちろんですが、とあるドラマで公式SNSを担当した際に軽くバズった時は、驚きとともに広報の面白さを感じました。
条件があるから、名作が生まれる
アシスタントプロデューサーとして実際にドラマを作る立場になったからこそ感じるのは、「作り手側になりたい」と思うことの大切さです。ドラマやテレビが好きなことはもちろん大切ですが、やっぱり「ドラマを観ることが好き」というだけでは、超えられない壁があります。ドラマを観ながら「自分だったら、脚本をこうしてみたい」「自分なら、このキャストにどういう人を持ってくるかな」といった、いわば“作り手目線”で考えることが好きな方は総じて長続きしていますし、良い仕事をされているように思います。
また、作り手が忘れてはいけない大切な視点が“受け手はどう感じるか”という点です。テレビに限った話ではありませんが「自分がやりたいから、やっちゃいましょう!」という簡単な話では、作品は作れません。「今の時代には、どんな作品が合っているのか?」「今の人たちは、どんな作品が見たいのか?」「この描き方はコンプライアンスとしてどうなのか?」「スポンサーにはこの表現は受け入れられないのではないか?」など、受け手にまつわるたくさんの制限や枠組みを考えることが求められます。それをマイナスと捉えてしまうととても窮屈な印象を受けますが、面白いものや趣向を凝らしたものを作るための“お題”のように捉えれば、名作を生み出すプロセスになり得ます。
夢は、いつか自分自身の好きな分野と世の中の人が求めるドラマが融合した作品を作ること。これからも、今を生きる人々に求められる物語を届けていきたいと思います。
※内容は、すべて取材当時(20年11月時点)のものです