
2050年の映像って、
どうなっているんだろう。
何ができるんだろう。


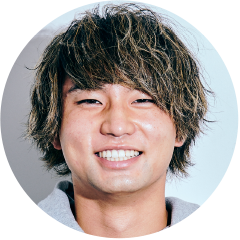
共同テレビの
新設部署、メディア
戦略室の役割。
田中:テレビ番組はもちろん、配信や企業のPR動画など映像コンテンツが多様化する中で、共同テレビ内にも「どんな映像コンテンツにも対応します」と言える部署が必要だね、という発想で作られたのが僕たちメディア戦略室です。まあ、いわば“何でも屋”的な部署。
安達:ジャンルの判断が難しい新規案件問い合わせがあると、まずはメディア戦略室に「こんなこと、できますか?」と問い合わせが来ますよね。
田中:そんなメディア戦略室において、僕自身は室長とプロデューサーを兼ねながら、組織と番組作りを担当していて、安達さんはプロデューサーと演出家としてたくさんの番組を手掛けている。一方、谷川さんは制作技術部の所属なんだよね。
谷川:はい。制作技術部に所属して、カメラマンをやらせて頂いています。メディア戦略室から「こういう撮影をしたいです」というお話がうちの部署に来ると、そこからカメラマンや音声スタッフが派遣される形ですね。なので、打ち合わせから参加する訳ではなくて、メディア戦略室からの依頼を受けて仕事が発生します。その意味では、お二人と僕の立ち位置は少し違いますよね。
安達:そうですね。最近は、逆に技術部から「こんな仕事の依頼が来たんだけど」というお話を頂くこともあります。その際は、メディア戦略室内で案件を検討して「制作チームが必要だね」となったら「一緒にやろう」という流れになります。もちろん、制作チーム側でCMだ、映画だ、ドラマだと企画する過程で「これは専門的な撮り方が必要だね」となったら、声を掛けさせて頂くこともある。色んなパターンがありますよね。
田中:そういうパターンの広がりは今後も増えていくことが予想されますが、その対応こそがメディア戦略室の使命の一つです。例えば、映像の多様化のひとつに視聴環境の変化があります。テレビを視聴する際に、スマホやタブレット、パソコンなどを操作しながら見ることが多くなってきました。若者を中心に「Twitterを見ながら番組を見る」といった傾向も高まっているので、そういった世代にもリーチできるデジタルデバイスと連動したテレビの作り方の模索も大切だなと考えています。
安達:確かに、その時間にチャンネルをピッと付けてテレビの前に座って見る、みたいな習慣は減りましたよね。あと、朝起きてご飯を食べている時でも“ながら”でテレビを付けてるという家庭が多かったけど、今、人の家へ遊びに行っても、別にテレビは付けてないですよね。子供の頃、お昼に友達の家に行くと必ず『笑っていいとも!(フジテレビ)』が流れていたのに。
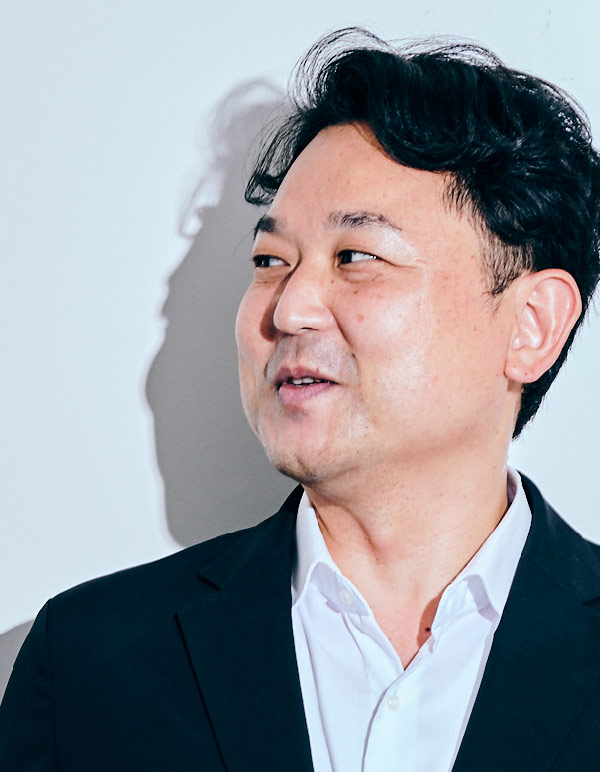


田中:変化に合わせて番組の作り方も少しずつ変わってきていますよね。例えば、ぱっと見て分かりやすい演出をするとか。
安達:サイドテロップを読めば何の番組をやっているのか一目で分かるようにしたり、ワイプ(テレビ番組内で右上や左上などに表示される小窓状の映像)も2個は必ず入れたりとかですよね。あれは、撮影側としても工夫していますよね?
谷川:そうなんです。ワイプもそうですし、例えば朝の番組だったら画面の左上の時報や他にも沢山の情報が入るので、それを踏まえて撮らなければなりません。 僕らが普通に「気持ちいい」と思って撮っている画角だと、顔にテロップサイドが乗ってしまうんですよ。だから、「気持ちいい」と思う画角よりも少し余白を多めにとる必要があります。
田中:そしてそれは“テレビ番組の場合”だよね。メディアが変わると、撮り方も変わってくるはず。
谷川:はい。例えば、ドラマや企業広告であれば、画面ギリギリまで自分の意図した映像を入れられます。媒体や番組によって全部違いますね。
安達:20年くらい前からそういう傾向はあったけど、ここ数年で一気に多様化が進んだ印象があります。

“画力”のパワーと、
その問題点について。
田中:映像が多様化する中で、今後はより“画力(えぢから)”が大切になってくると考えています。以前、とあるYouTuberさんとお仕事した時に、彼が「TikTokやYouTubeのショート動画など数秒のメディアが増えると、“画力”がないとすぐに飛ばされちゃう。だから、とりあえず“ポップコーンを大量に作ってみた”みたいな強い画を頭から並べるんです」と仰っていたんですよね。それは、その通りだなと思いました。結局、引きがある画や一発で分かるネタの強さみたいなものが重視されていると思います。
安達:その通りですね。それで、サムネイルの画が気になって中身を見ると、期待したほどではない動画がたくさんある。これってテレビとYouTubeの大きな違いだなと思っていて、テレビはやっぱり“CMを見てもらってなんぼ”という所があるからなんですよね。
谷川:そうなんですよね。
安達:テレビ番組は、スポンサーさんにお金を出して頂かないと番組が存続しないから、しっかりした中身を作ってCMを挟んで…という形が成り立つ。でも、YouTubeは基本的に再生回数をいかに増やすかが大切になっている。もちろん、近年はYouTubeにおいても視聴時間や動画の質、CMが入るタイミングなどが重要になってきているので、一概には言えませんが。
谷川:その意味では、同じ配信でもNetflixやAmazon Prime Videoなどは、少し違うのかもしれません。あれって、テレビで流しているドラマやバラエティ、映画が、配信を通じて見ることができるってだけですよね。そのため、内容はテレビとあまり変わりません。その意味では、「Netflixだからこういう撮り方です」とかは、あまりないのだと思います。



田中:内容も作り方も変わらないけど、視聴者との向き合い方が違うんでしょうね。例えば、テレビで面白そうな番組があったとして、「これ見たいな」と思っても見逃すことがあるじゃないですか。放送も終わっているしTVerもないし、みたいな。その点、Netflixだといつでも見ることができますよね。自分の好きな時に好きなものを見る、いわば“目掛けて見る”感じが、今の習慣にすごく合っているのかなと思います。
安達:そんなNetflixも、最近“CM入りプラン”や“CMをカットする有料プラン”が出てきている。結局、少しずつテレビと似た状況になってきてるんですよね。

2050年の映像って、
どうなっているんだろう。
田中:お二人は、30年、40年先の映像メディアってどうなっていると思いますか?
安達:もう定年してるだろうから、分かんない(笑)。
谷川:逆に30年、40年前に遡ると、1990年頃じゃないですか。先輩から話を聞くと、当時って4対3の四角いブラウン管の画面で、カメラもめちゃめちゃ大きかったらしいんですよね。それで、15分や20分しか回らないテープや重いバッテリーを何十本と持っていた、と聞きました。それが今や記録はSDカードになって、バッテリーは一本挿せば何時間も回って、カメラも小さく軽くなって、さらにテレビは16対9の4Kで極薄になっている訳です。で、これがさらに30年経ったらどうなるか…なんて、もう分からない(笑)。
田中:ただ、8K、16Kの時代は間もなく来ますよね。
谷川:これは現時点でも既に耳にする話なんですが、8Kとか16Kとかになったら、恐らくカメラを一台置いておけば切り抜けるようになるんですよ。今までは、「この人を撮るにはこっちにカメラ置いて」「この表情を撮るにはこっちにカメラ置いて」といったように、カメラそれぞれに役割を持たせて数台で番組を撮っていたのですが、8Kとか16Kだとカメラ2台ぐらいを置いたら、あとは編集でどうにでもなる。画質が良すぎるので、わざわざ現場で寄ったり引いたりしなくても、パソコン上で処理できるんですよね。
田中:カメラを据え置きにして一人でスイッチングすれば、8カメ分の役割を一台で賄えちゃうようになる。こういう“変化するタイミング”っていろんなチャンスが転がっていて、特に人と人とのコミュニケーションや連携が大切になってくると思うんです。
安達:まさにそうですよね。僕、共同テレビってすごく良い会社だと思っているんですよ。なぜなら、色んな“ハブ”になれるから。例えば、ここで同席している我々であっても、技術チームも制作チームもいる。社内を見渡せば、ドラマもスポーツもバラエティもやっている。番組作りだって、フジテレビのみならず色んな局とやる。「節操ない」って言えばそうかもしれないけど(笑)、僕としては“業界の真ん中にいる”感じがするんですよ。
谷川:確かに。第3制作部では、イベントもやっていますよね。
安達:そうです。舞台の演出に関わることもありますし、イベントで日本全国を回ることもある。
田中:いい意味でも悪い意味でも、止める人がいない会社なんですよね。自由な発想で、面白そうだったらチャレンジさせてくれる文化がある。「いいじゃん、やれば?」みたいな。チャンスに溢れていると思います。
谷川:お二人が言われた通り、共同テレビには、色んな所に行くための“窓口”がありますよね。大手キー局から配信、イベントを含め、話を聞いてくれる人や部署がある。
田中:実際、これまでのテレビ局はもちろん、最近は企業やYouTuberといった様々な方々からお仕事のご依頼を頂く機会が増えてきました。私たちメディア戦略室は、まさにそこに対応して、何かを生み出す組織にならなければいけないですね。
安達:それがまさに“ハブ”ってことですよ。共同テレビの社員がハブになって、テレビや配信、イベントのいい所をくっつけようっていう。…最後、意見をまとめて、いいこと言った風にしてみました(笑)。
