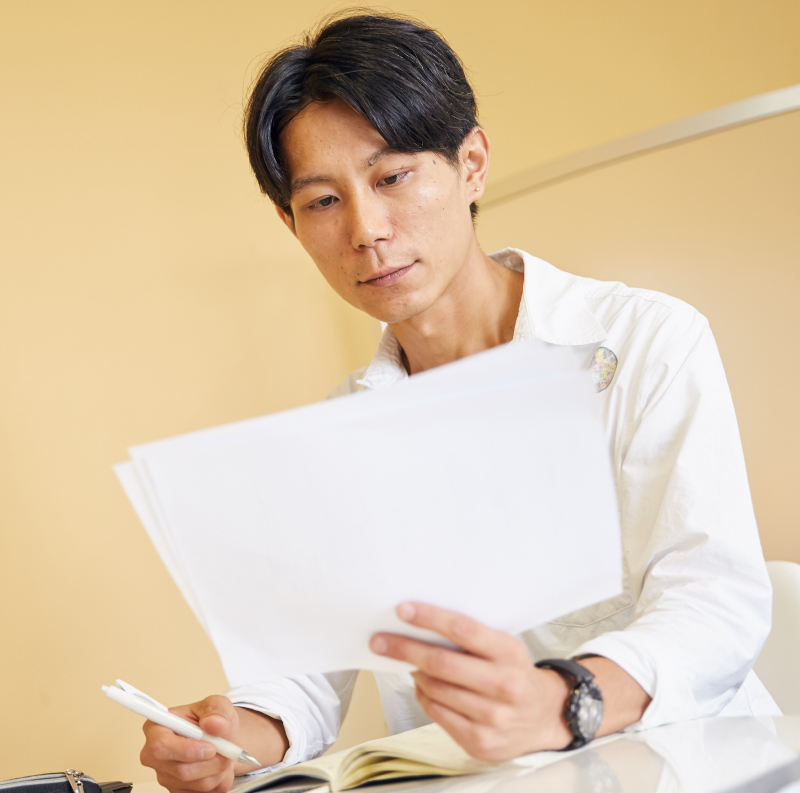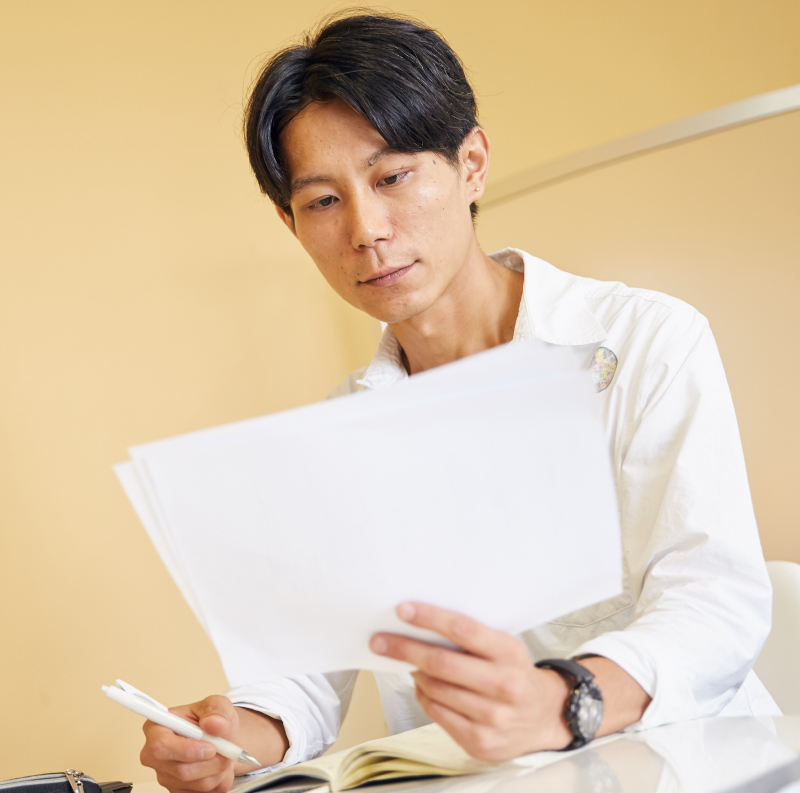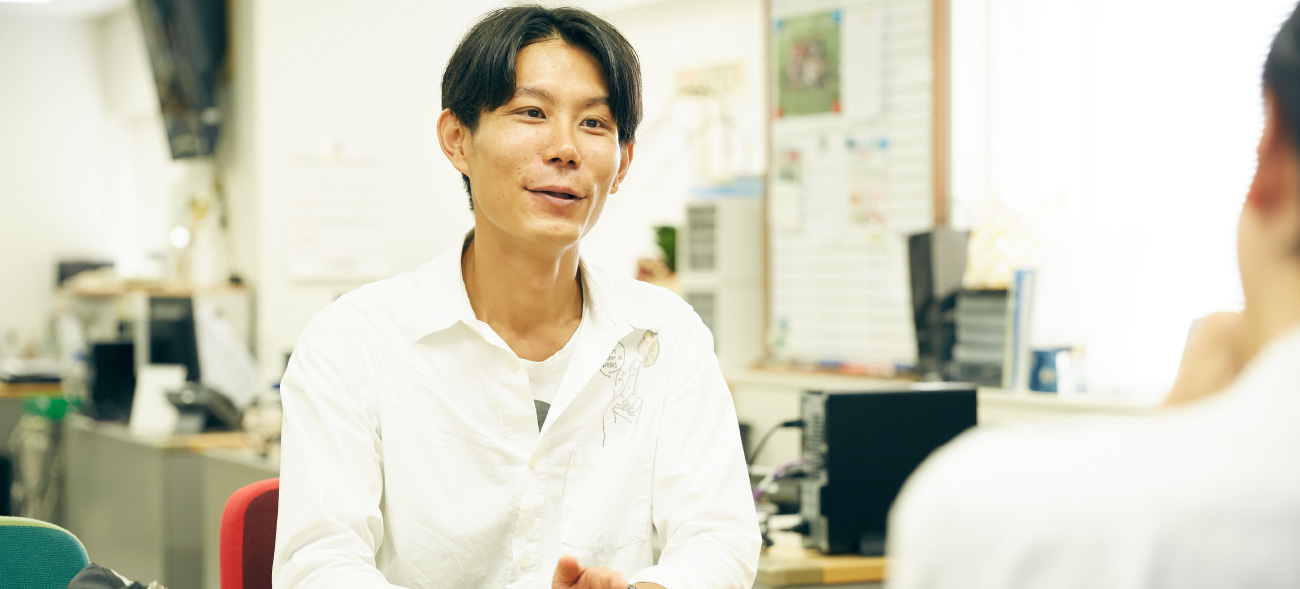脚本、美術、画面作りまで、
すべてに関わる
現在は、主に監督としてドラマ制作に関わっています。作品全体の舵取りをおこなう監督は、通称“本打ち”と呼ばれる脚本家やプロデューサーとのシナリオ制作から関わり、キャスティングや美術打合せ、衣装合わせや技術打合せといった様々な領域のプロとのやりとりを通じて内容を決定していきます。また、打合せに際しては「脚本にあるこの“企業”とはどの程度の規模なのか」「大企業だとしたらどんなオフィスなのか」「この人物が着るワンピースは明るいのか暗いのか」「番組全体の色味やトーンはどうするか」といった細かい表現まで踏み込み、イメージを共有します。いずれも“答えがない”作業なので、信じられるのは自分の感覚と信念。作品性や伝えるべきことを踏まえて、監督である自分自身が「こうすべきだ」と思ったことを信じ、判断を重ねます。
“やれることをやる”ことが、次の現場のヒントになる
共同テレビで育ってよかった点は“できる範囲でやれることをやる”という視点を学べたことです。ドラマ制作の現場は、いつも恵まれた状況だとは限りません。機材トラブルが発生することや、急きょ役者に別の仕事が入ってしまうこともある。そんな中でもやらざるを得ない場面が実はたくさんあるのですが、共同テレビに関わる人と現場は、その“怖さと乗り越え方”をいつも教えてくれたのです。例えば、最近私が経験した現場では、50名来るはずのエキストラが10名しか来ませんでした。役者もスタッフも勢揃いでエキストラだけいない訳ですから、やはり焦りますよね。ところがそこで思い出したのが、助監督時代に見ていた先輩監督の姿。ほとんど同じ状況下で、その先輩監督は撮影や演出の工夫で“10名のエキストラを30名に見せること”に成功していたんです。想定外の状況は、必ず発生するもの。だからこそ、ただ諦めるのではなく“いまできるベストを尽くす方法”を学べたことが、私の大きな糧になっています。
これは、ひょっとしたら個人のキャリアにもいえるかも知れません。ドラマ監督を目指していれば、想像以上のハードルや失敗に出会うでしょう。ですが、そこで諦めてしまっては何も残りません。例えば“10年”と決めて本気で向き合っていれば、きっと壁を越える方法を学べるはず。共同テレビは、個人にチャンスを与えられる環境とパワーがある会社です。諦めたくない方は、ぜひエントリーしてください。
※内容は、すべて取材当時(19年10月時点)のものです